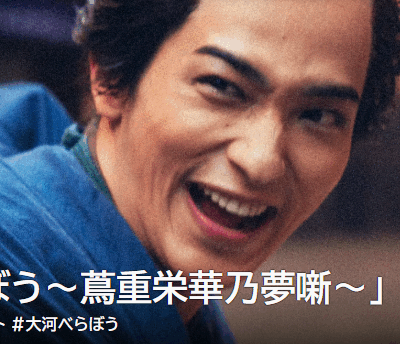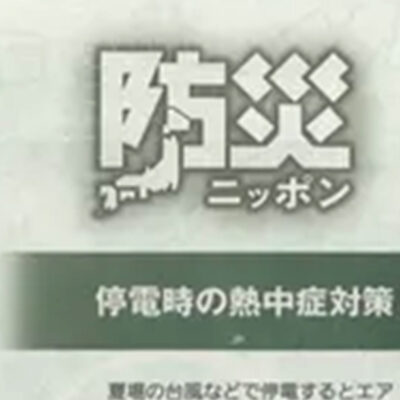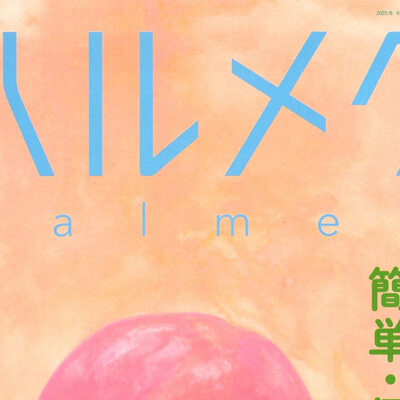- 2012/01/20
- 風呂敷の知識
家紋入り風呂敷の由来 ~風呂敷の歴史~
みなさま、こんにちは。
京都の風呂敷製造・卸、山田繊維㈱の杉江です。
前回お話しした風呂敷の歴史の続きになりますが、
ちょっと振り返ってみます。
風呂はもともと蒸し風呂、イメージとしてはサウナのようなものでした。
さてどのくらいの間隔で入っていたと思われますか?
身を清めるために行うものでしたので、妙心寺では、
4と9が付く日に沐浴がされていました。
4(死)、9(苦)から解き放たれるこの日に
されていたと推測されます。
また月に1度、「施浴」という看板が掛けられ、
一般にも浴室を開放していたとされています。
貧しい人々や病人、囚人らを対象に
施浴をしていた寺院もありました。
この入浴も現在のようにハダカでなく、
白衣を着用し入ることが作法であったようです。
時を経て、室町時代の風呂も蒸し風呂でしたが、
将軍義満は大湯殿を建て、
ここに大名を招いたという記録が残されています。
入浴の際、他者の衣服と間違えないように
家紋が入った布で自分の衣服を包んだようです。
またこの布上で着衣を整えたといわれ、
一説に、この敷布を風呂敷と呼んだ起源とされています。
家紋が入っており、誰のものかすぐに識別できますが、
ここである疑問があります。
家紋が入った布上で着替える・・・
大切な布の家紋部分を踏んだり、
腰をおろし、着脱をしてなかったでしょうか?
家紋(家系)を汚すといった行為とも取れないでしょうか?
少し考えすぎかもしれません。
さて皆様はどう考えられますか?
京都の風呂敷メーカー山田繊維㈱の杉江でした。